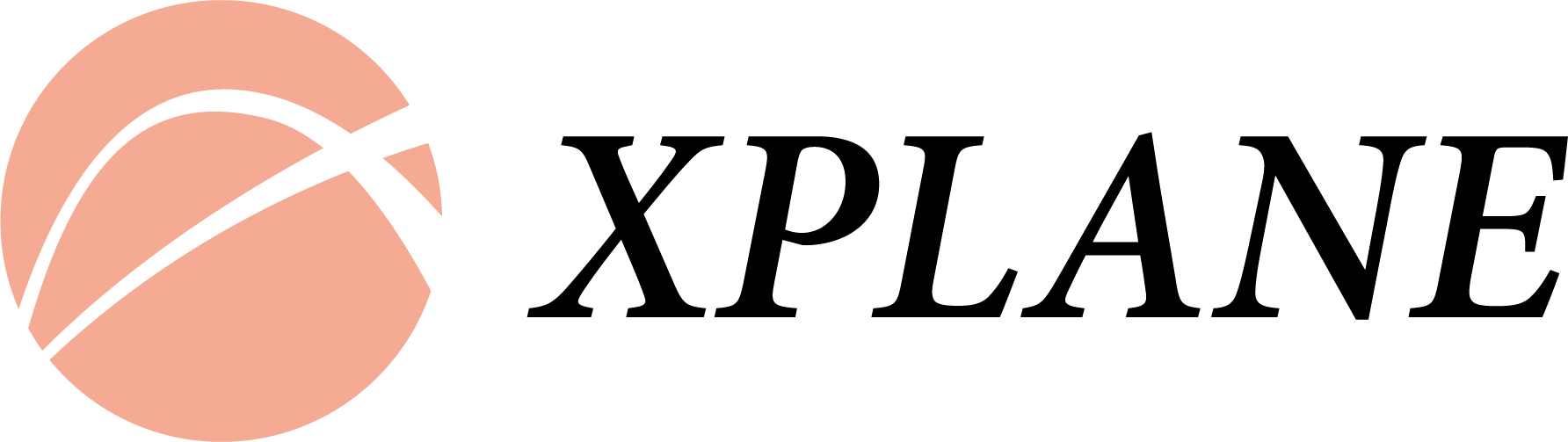面接
面接 (On-site Interview)
1. 海外大学院受験におけるInterviewとは? ??
大学院受験における「面接試験」と聞いてどのようなものを思い浮かべますか?日本の大学院の一般的な面接試験といえば、面接官である教授数名の前で自分の過去の研究の内容をプレゼンしたり、受かった後の研究予定、あるいは一般的な知識問題に答えるようなものを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。決められた日時に大学に行き、長くて1時間、短くて十数分のケースも少なくないと思います。筆記試験を突破した後のオマケのようなものと考えている人も少なくないのではないでしょうか。
一方、アメリカの大学院のInterview (面接)、特に学生が現地に招待されて行われるOn-site interviewは上記のような面接とは全く異なります。On-site interviewとは大学が学生を招待して行われる、各研究室と大学院生候補とのマッチングを吟味するためのプロセスです。面接だけではなく、大物教授によるレクチャー、教授や現役学生との交流なども行われます。面接が二日以上行われることはざらで、Harvard Universityなど特にお金のある大学は3-5日泊まり込みでの面接になることもあります。「面接」というよりも「合宿」に近いかもしれません。そこでは、自分の希望する指導教官だけでなく、その学部の関連分野の教授4人から多いときは20人程度と終日面接が組まれ、一日中自分の研究と将来の研究アイデアをプレゼンすることになります。
そしてほとんどの場合、on-site interviewは面接のみにとどまりません。面接の合間にはその大学が誇る教授陣による大学院生候補のためだけに向けたレクチャー、学部の魅力を紹介する現役学生によるプレゼンテーション、そして全ての行程が終わった夜にはその現役学生達と街に繰り出したりと楽しいイベントが盛りだくさんです。さらに、大学までの飛行機や電車などの旅費はもちろん、滞在先のホテル、面接期間中の食事、そして締めのパーティまで、全ての費用が大学側によってカバーされます!
至れり尽くせりのこのイベントが、「大学院入学のための面接」であることが信じられない人もいるかもしれません。なぜそんなことをする必要があるのでしょうか?それは学生が何校でも併願できるアメリカの大学院では、学生側の競争だけではなく大学院側が優秀な学生を取り合う競争があるからです。現地で行われるInterviewは、学生が面接を通じて自分の実力を証明する場所としてだけではなく、大学がいかに自分たちの環境が素晴らしいか売り込み優秀な学生を獲得する機会として機能しています。それは、大学院生こそが研究を進めていく主人公であるという認識があり、究極的には輩出する大学院生の質がその大学の評判の重要なファクターを担っているからです。
2. 大学院 Interview のいろは
呼ばれる時期
大学院の面接への招待が来るのは、出願の書類の提出期限から数えて早くて約2週間後、遅くて1ヶ月半後頃です。この面接に呼ばれるためには、’Short List’、つまり出願者の中から上位20-30人程度に入る必要があります。つまり、面接に呼ばれた時点でその出願者は呼ばれていない学生より合格する可能性がはるかに高いと言えます。さらに留意しておきたいのが、Short Listの中でも上位の者ほど早く面接に呼ばれる可能性が高いということです。これは、優秀な学生は複数の大学院から面接に呼ばれる可能性があり、面接の日程が早々に埋まってしまうということがあるためと考えられます。また、より人気のある (≒その分野での評判が高い) 大学院の方が候補生を面接に呼ぶ時期が早くなる傾向があります。
面接のスケジューリング
面接の時期は大学によって様々で、多くは1月末から3月中旬の数日間で行われます。出願者が優秀かつ複数の大学院に出願した場合、高い確率でInterviewの日程が被ってしまいます。「A大学もB大学もこの週に on-site interviewをやるため、どちらか一つしか行けない」という状況が生まれるということです。出願者にとってA大学かB大学どちらにより興味があるかはっきりしている場合は問題になりませんが、どちらにも興味があるという場合は大学に問い合わせて別の日程でon-site interviewをしてもらえないか交渉してみましょう。多くの大学が学生を複数にグループ分けして時期をズラして面接を行なっており(注: 一般的に第一グループの学生が合格レース上位であることが多い)、大学によっては数週間に渡ってInterview weekを設けているところもあります。
面接の形式と準備するべきこと
面接に呼ばれて次に行うことは、面接に向けた準備です。そのためにはまず一般的な面接の形式を知っておく必要があります。米国大学院の面接で最も一般的なのは教授と一対一で行う30分間程度のミーティング、そしてそれを教授の数に応じて複数回行うという形式です。その他にも、教授二人と学生一人、あるいは教授数名と学生数名というケースもありますが、これらは多くの学生を大量に捌かなければならない Skype interview (Off-site interview) のような場面で見られることが多いです。30分間の面接を自分の希望する指導教官に加え関連分野の教授数名、さらには同じ学部ではあるが異なる分野の教授数名と繰り返すという形式が一般的です。
面接で訊かれること
もちろん大学や教授によりますが、頻繁に問われる質問を以下にまとめました。
あなたがどんな研究に興味があるか1-2分で説明してください
あなたの過去の研究経験を簡単に説明してください
なぜこの大学のこの学部に応募しましたか?/どの教授を志望していますか?
この大学でやろうと思っている研究のアイデアはありますか?
このような質問から始まり、そこからその教授の興味や議論の方向によって面接は自由に発展していきます。例えば教授の興味が出願者のそれに近ければ、過去の研究の詳細をさらに掘り下げる方向に議論が発展するかもしれません。あるいは、出願者がその大学に進学して挑戦したい研究を議論するのに大半の時間を費やすこともあります。この面接では (CVやエッセイを見れば分かるような) 研究に関する実績や理解度を見ているというよりは、いかに自分の興味関心を分かりやすく簡潔に伝えることができ、その上で興味深い議論を教授レベルの人とできるか、という能力を試されています。自分の研究を専門外の教授に分かりやすく伝えるためには、研究の本質をしっかりと理解しておく必要があります。
最後に、面接における一般的なTipsをまとめておきました。面接に招待されるということは、夢の大学院合格まで後一歩です。納得のいくまでしっかり準備して本番に臨みましょう!
1. 分野外の人にも分かりやすく話そう。
昨今の研究は専門化が進んでおり、どんな有名大学の教授でもあなたの卒論や修論に関しての専門的な知識を持っているとは限りません。分野特有の専門用語をなるべく使わず、なぜその研究が重要かつ面白いか理論的に話すことを心がけましょう。英語が苦手だと自覚している人は、自分の研究の要点を簡単な英語ではっきりと話せるように準備してください。
2. 手短に話そう。
自分の研究興味や過去の研究の話を始めると、熱が入るあまり長々と話してしまう人は少なくありません。しかし、よほどの研究でない限り、どんな内容でも2-3分で要点を話すことは可能です。また、細かい技術的な手法に固執して、研究の主な目的から逸脱しないように気をつけましょう。
3. 情熱を込めて話そう。
面接では、教授たちは知能だけでなく出願者の情熱を審査しています。同程度の優秀さであるならば、淡々と説明しているような人よりも、目を輝かせ情熱を込めて思いを伝える学生を取りたいと考えています。母国を離れ異国に来てまで研究したいと考えているその熱意をストレートに相手にぶつけましょう。
DISCLAIMER: この情報は生物学系の米国大学院に現在所属する筆者の経験を元にした記事情報です。他国の大学院、米国内他学部の大学院の面接形式と異なる場合があります。